SNSはうつ病の時にやめるべき?
こんな疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと「向き合い方を間違えなければ」辞めなくていいです。
というのも、SNSが回復の助けになることも多いから。
うつ病経験者のぼくもSNSで情報発信をしていますが、「励まされた」とのリプライやいいねをたくさんいただいています。
ぼく自身がうつ病の時は、メンタルヘルスの発信をしている人が少なく
当時、同じような人がいれば少し楽になれたかもな
と感じたほど。
一方で、向き合い方を間違えると症状を悪化させてしまう危険性も。
ぼくもうつ病初期のとき、SNSとの向き合い方は大苦戦しました。
この記事では、うつ病に悩む人がストレスなくSNSと向き合うためのポイントや、SNS疲れを防ぐために実際行った対策を紹介します。
「SNSに疲れた……」と悩む人は、ぜひ最後まで読んでみてください!
悩みを話せなくて困っているあなた、1度ぼくに話してみませんか?
- 主に「うつ病からの社会復帰」や「今の仕事でいいのか?」といった悩みを解決
- これまで140人以上の悩みを解決し、94.6%の方が満足
- 「メンタル心理カウンセラー」資格保持
\そのモヤモヤ、スッキリに変えます/
うつ病のときにSNSでやめるべきポイント

うつ病の時にSNSでやめるべきポイントは、以下の3つです。
- タイムラインをあまり見ない
- 人を傷つけ、悲しませることをしない
- 「うつは甘え」と言う人と距離を置く
1つずつ解説していきますね。
ポイント①:タイムラインをあまり見ない
1つ目は「SNSのタイムラインをあまり見ない」ことです。
SNSのタイムラインには、励まし合う言葉や有益な情報などがたくさんあります。
これらを見たり、フォロワーさんの投稿にコメントしたりすることはとても大切です。
一方で、FacebookやInstagramなど「幸せなワンシーン」ばかり投稿するSNSには要注意。
なぜなら、リア充投稿を見ては、以下のようなことを考えてしまうからです。
(すべて、ぼくが実際に思ったことです)
- あいつはあんなに幸せそうなのに対して自分は……
- 自分も楽しそうな写真を撮りたい人生だった
さらに、病気の特性も合わさって「自分には価値がない」と考えるようになってしまいます。
とはいえ、1人1人ブロックやミュートをしていたらキリがないですよね。
そのため「タイムラインをあまり見ない」ようにすることがおすすめです。
タイムラインをむやみに見ては悲しい気持ちにならないように、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 時間を決めて見るようにする
- 仲いい人の投稿だけ見れるリストを作る
- あまりにもストレスになる人はミュートする
自分が「しんどいな」と感じることに対し、自分から距離を置く。
これが、SNSとうまく向き合うための秘訣ではないでしょうか。
ポイント②:人を傷つけ、悲しませることをしない
2つ目は「人を傷つけ、悲しませることをしない」ことです。
うつ病は特性上「誰かに認められたい」と感じるときがあります。
こうした承認欲求は健康な時でもありますが、うつ病と戦うときの承認欲求は少し違ったりします。
闘病中に自分で気づくのは正直難しいですが……。
「人を傷つけ悲しませることで、認めてもらおうとする場合」が一定数あるんですよね。
- リスカ痕
- 大量の薬の写真(OD)
- 「自分のほうがしんどい」というマウント取り
といった内容で。
こうしたことがないように「前向きに、かつ優しい言葉で発信する」のをおすすめします。
しかし、闘病する間につらいときもあると思います。
ぼくも、闘病中何度も何度も苦しみ、なんどもくじけそうになりました。
気持ちを溜め込みすぎてしんどくなった人が多いでしょうし、正直に気持ちを吐き出すことは悪いことではありません。
「しんどいのを察して!」とほのめかす内容ではなく
- なぜしんどいのか
- どういったことでしんどくなったのか
を書くと、誰かがアドバイスしてくれるかもしれませんよ( ˘ω˘ )
ポイント③:「うつは甘え」と言う人と距離を置く
3つ目が「『うつは甘え』と言う人と距離を置く」ことです。
ぼくもうつ病に関する情報発信をしていると
- 甘え
- 社会不適合者
- 病名出すやつにはロクな人がいない
といったリプライや引用RTが定期的に飛んできます。
なんなら、闘病中にネットストーカーからも言われたことも( ゚Д゚)
ただ、闘病と情報発信を通じて1つのことに気づきました。
「うつは甘え」と言うタイプの大半は、実は自分もしんどい思いをしているということに。
- あいつだけ働かずに休んでせこいわ
- 自分は理不尽な上司に耐えてるのに
- 楽しくない毎日だけど、生活のために我慢してるのに
こんなことを心のどこかで思っていることから、苦しんでいる本人に「うつは甘え」ということでストレスを発散します(;^ω^)
もしくは、思いやりの気持ちがない「サイコパスタイプ」かのどちらか(笑)
どんなに仲のいい人であろうと、親しい人に対し「うつは甘え」と言ってくる人とは将来的に衝突する場面が出てくるでしょう。
あなたの心の安全を守るためにも、「うつ病をきっかけに距離を置く」ことをおすすめします。
あなたのことを大切に思っている人であれば、もっと優しい言葉をかけてくれるはずですからね。
うつ病の人がSNSをやめる原因「SNS疲れ」

うつ病の人がSNSをやめるきっかけとして多いのが「SNS疲れ」。
特に、10代から30代でうつ病に悩む人ほど感じやすいです。
この章では、そんなSNS疲れになりやすい原因と対策を紹介します。
SNS疲れの原因
SNS疲れをしやすい原因は、以下の2つです。
- 周囲に対する劣等感
- 理解がない人からの言葉
詳しく見ていきましょう。
①:周囲に対する劣等感
1つ目は「周囲に対する劣等感」です。
学生だと進学や就職、20代~30代の社会人は結婚や出産・マイホームの購入などを報告するような投稿が多いのではないでしょうか。
うつ病と戦っている間は、自分だけ「時が止まっている感覚」を感じやすいです。
親しい人の嬉しい出来事には本来喜べるはずですが「何やってるんだろう自分……」と悲しい気持ちの方が上になってしまいます。
加えて「身近な人の幸せを喜べない自分は最低だ……」とますます自己嫌悪するのもつらいところですね。
②:理解がない人からの言葉
2つ目は「理解がない人からの言葉」で、回復期に多い印象。
うつ病がひどかったころに比べると体調も良くなり、買い物に行ったり、友達とお茶したりできるようになります。
しかし「久々に遊んで楽しかった!」といった内容を投稿すると……
- うつ病なのに遊びには行けるん?
- 遊びに行けるなら働けよ
- サボってるだけなんじゃない?
ということを言われることがあるんですよね。
SNSの投稿でも言われたことありますが、1番つらかったのは「会社の同期」から言われたこと(今はこの会社辞めてます)。
当時交際していた彼女の前ですごくイライラしてしまい、申し訳ない気持ちになってしまいました。
「遊びに行くことができる」というのは、うつ病から復活するには欠かせないステップです。
しかし、「働かざる者食うべからず」と考える人が多いのも事実で、攻撃的に接してくる人も一定数いるんですよね。
SNS疲れを防ぐには?
そんなSNS疲れを防ぐには、どうしたらいいでしょうか。
実際、ぼくが対策した以下の方法について、経験談を交えながら紹介します。
- Facebook、Instagramをアンインストール
- Twitterのタイムラインを見ない
- 打ち込めるものを作る
いわゆる「リア充SNS」をアンインストールするだけでなく、タイムラインを見るのも控えるようにし、徹底的に幸せ投稿から離れるようにしました。
なぜなら、SNSの投稿を見るたびに「取り残された感覚」を感じ、毎日のように絶望していたからです。
- 親友が立て続けに結婚
- 出産報告も定期的に流れる
- パワハラなどで仕事も楽しくない
こんな状況だから、何を生きがいにしていいのか全くわからない。
SNSで流れてくる「他人の成功」を見ては、自分のみじめさに何度も泣きました。
また、うつ病には「希死念慮(〇にたくなる気持ちが現れる)」という症状があります。
幸せな人と気づかぬうちに比べ、自分の存在価値が減っていってしまう状況ですね。
そんな自分はというと……
うつ病の半年前になった「適応障害」時代に、1年以上付き合った彼女を振ってしまいました。
このことから、「恋人ができた」「結婚した」という報告を聞くたびに、『なんで振ってしまったんだろう』と後悔していました。
加えて、倒れる直前に会社で昇格したのもあり
仕事もプライベートも脂がのってくる時期に、自分はなんでこんなことになってるんだろう……生きる意味あるのかな
と、みじめになった回数は数え切れません。
とはいえ、今もこの記事を書いているように生きていますし、社会復帰も一人前にできています。
今となって当時を振り返って
リア充SNSを消すなど、幸せな情報が目に入らないようにした
ことと
ボカロPとしての曲作りに集中して、SNSを見る時間を減らした
という2つが、回復には効果的だったと思います。
いくらいい「薬」でも、多すぎると「毒」です。
必要以上にSNSを見て傷つかないように、ほどほどに向き合いたいきたいものですね。
まとめ:SNSはうつ病の人がやめるべきポイントを知ってから楽しもう

この記事では、SNSをうつ病の人がやめるべきかどうかについて解説しました。
うつ病の時にやめておきたい3つのポイントは、以下の3つでした。
- タイムラインをあまり見ない
- 人を傷つけ、悲しませることをしない
- 「うつは甘え」と言う人と距離を置く
それに加えて
- 周囲に対する劣等感を感じやすい
- 理解がない人からの言葉で苦しくなる
といったこともたくさんありますので、自分からこういった人や情報をシャットアウトすることも大切。
ただし、SNSとうまく付き合うことが回復の助けになることも多いです。
ぜひ、自分なりの向き合い方を見つけてくださいね(`・ω・´)
最後になりますが、もし困ったときは「筆者じんとへのオンライン相談」もぜひご検討いただければと思います。
1人の当事者として悩みを聞きますので!
ではでは、今日も生きててえらい。

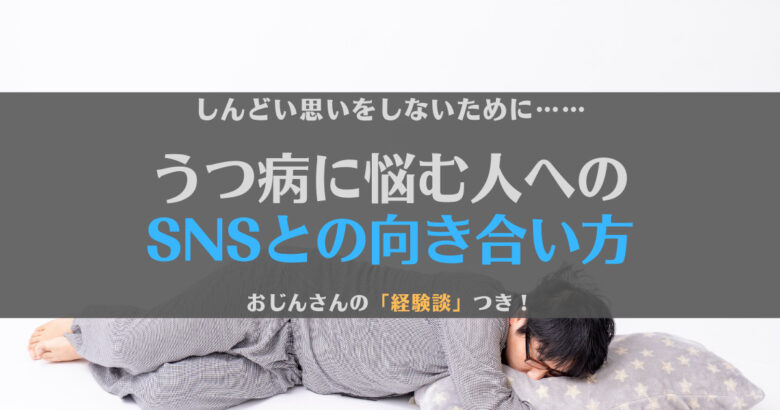

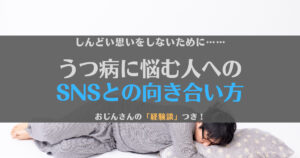
コメント